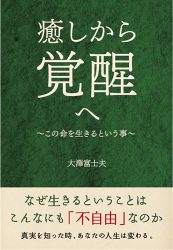年を取ってきたせいなのか、最近妙なことに感動したり今まで当たり前と感じていたことに感心してみたりすることが多くなってきました。たとえば、蛇口をひねると飲める水がいくらでも出てくることに何て贅沢なことだろうと思ってみたりするのです。井戸に水を汲みに行っていた時代を経験してない自分ですから、その時代と比べる必要はないと思いながらも、心のどこかでふと便利だなと感じてしまったりするのです。
この便利さというのは我々人間にとってどれだけ大切なものなのか、少し考えてみるといろいろなことに気づかされます。便利さを求めることは効率を向上させることと似ています。人は効率を向上させることを原始時代から一貫してやってきているとも言えます。お腹が空いたら漁に行ってさかなを獲ってきて好きなだけ食べる。またお腹が空いたときには、前回のさかなは腐ってしまっているので、また漁に出かけて獲ってきた新鮮なさかなを食べる。
これを繰り返している間に、獲ったさかなの食べ残しを偶然涼しい土の中に置いておいたら、次にお腹が空いたときまで腐らないことを発見して、そこから食べ物を保存することを覚えたのです。保存できるとお腹が空くたびに毎回漁にでかけなくてもいいことに気づいて、漁の効率が上がったのです。これは漁が危険だったり、重労働だと感じている者にとってはとても便利なことであるわけです。
またある者は、人が保存してあるさかなに目をつけて、自ら漁に出かける代わりに自分が作った何かの道具とさかなを交換することを思いつくかもしれません。こうやって物々交換という大変便利で効率的な生き方を体得していくことになったのでしょう。ここで大切なことは、漁をすることが楽しみの一つである人にとっては、さかなの保存も物々交換も大した興味の対象ではありません。生きるため、食べるためだけに漁に出かけていた人にとっては、そのような新しいシステムに魅力を感じるのです。
確かにやりたくないことを仕方なくやっている時ほどいやな時間はありませんね。その時間はとても長く感じるし、極端にそういったことばかりが続いたら何のために生きているのだろうと考えるようにもなるかもしれません。その時間を何とか頭をひねってできるだけ短縮することができたらいいなと思うのは当然です。その時間を別のやりたいことや休息などに当てることができたら、人生が楽になるのは言うまでもありません。
人が便利さや効率的なものを求めて様々なものを開発してきた理由は、勿論いやなことを減らすという目的以外にも、たとえば人間の好奇心を満たすためという側面などもあります。ただ単につまらない移動時間を短縮するためにクルマが開発されたり飛行機が発明されたわけではないですね。できるだけ速いスピードで走ってみたいという熱意や、鳥のように空を飛んでみたいという好奇心を実現するためでもあったのです。
しかし、スキー場にリフトが設置されることがなかったら、これほどまでにスキーやスノボーに人気が出ることもなかったはずです。山の斜面を気持ちよく滑り降りるのが目的であるのに、滑っている時間はほんの数分だけで、また雪の斜面を重いスキーやスノボー板をかついて30分以上も費やして苦労して登らなければならないとしたら、スキー場に出かける意欲は激減してしまうでしょう。このように心地よく目的を達成するためには、効率的なことはとても大切なことなのです。
自分が目的とすること、やりたいこと以外のことをしなければならない時に効率を上げたくなるのが人間の常であることが分りました。だとすると、日頃から効率アップをいつもどこかで考えて暮らしているとしたら、それはやりたくないと思っていることを沢山しているからに他なりません。部屋の掃除をするのは、一般的にはきれいにするのが目的であって掃除すること自体が目的ではないですね。だからこそ掃除機その他の効率的な道具を使おうとするのです。
でも部屋の掃除を楽しくできるとしたら、少し話しが変わってきます。例えば最新鋭の掃除機を購入した直後だとしたら、いつもと違った気持ちで掃除ができるかもしれません。このときには、きっと効率を求める気持ちは減っているはずなのです。早く目的地に着かないかなと思って乗っている満員電車でも、たまたま座れて読みたかった本を読めたとしたら、目的地に着いてももう少し読んでいたかったと思うでしょう。
いつもいやだなと思っているクルマの渋滞も、あこがれの人とのデートだったら全然苦にならないかもしれません。彼に送ってもらう帰り道も、もっと一緒にいたいからわざわざ遠回りをして、それでももう家に着いてしまったと早く時間がたってしまうことを呪う気持ちになるかもしれません。こんな時にも人は効率を求める心をなくしているのです。
手作りのよさには、効率を求める意識とは違う心地よさのようなものがあります。大量生産によって製造されたものよりも、一つひとつ心を込めて作られたものは高価だったり時間がかかったりしますが、そういったもののよさには、それを作る人がその時間を楽しんでいることが重要な要素となっているような気がするのです。お母さんが握ってくれたおにぎりと、型で作った形の整ったコンビニのおにぎりとの違いのようなものです。
こうして考えてみると、効率を求めずに生きている時間が多い人の方がそれだけ人生を楽しんでいるのではないかと思えてきます。自分の毎日の生活を見つめてみた時にみなさんはどうでしょうか?本来の目的ではないことをするときに、それをできるだけ効率的に処理しようとするのか、あるいはその時間をできるだけ楽しめるように工夫しようとするのかで、人生は大きく違ってくるのかもしれません。
過酷な雪山を登山する人々にとっては、頂上に到達することは見かけの目的であって、悪条件の中を頂上まで登る過程そのものを楽しんでいると考えることができます。人生も同じように、我々は誰しも死という到達点に向かって生きていますが、死が目的ではありません。死ぬまでの過程をできるだけ楽しめるようにすることが大切なのです。辛いし思うようにいかないからと効率を求めて早く死に近づこうとするのではなく、どうしたらこの一瞬一瞬を楽しめるかを真剣に考えるのです。
いつだったか、アフリカのどこかの国の子供たちが、毎日2時間かけて生活に必要な水を汲みに行くのが日課だという番組を見たことがあります。子供たちはその時間の効率化を考えるというより、てくてく歩きながら兄弟や友人との会話を楽しんでいるのです。蛇口をひねれば飲料水がいくらでも出てくる生活を送っている我々現代人と、毎日2時間かけて水を汲みに行く彼らの生活では、一体どちらが精神的に豊かな生活を送っているのか、よく見つめてみる必要があると思います。