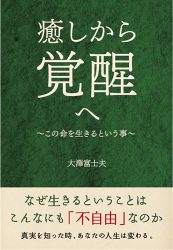人は誰でもみな、大好きな人やお世話になった人にプレゼントをしたことがあるはずです。相手の喜ぶ顔を思い描いたり、感謝の気持ちを込めたりして送るはずです。また、誰かからプレゼントをいただいて、とても嬉しい気持ちになった経験があると思いますが、そんな時、相手にお返しをしなければと思うかもしれません。誕生日のプレゼントを頂いたら、相手の誕生日には何をプレゼントしようかなって思いますね。でもなぜお返しをしようと思うのでしょうか?そんなの当たり前過ぎて考える必要もないと言われるかもしれません。礼儀をわきまえた人なら誰でもお返しをすると思われるかもしれません。
しかし当然のことと思わずにもう少しこのお返しについて考えてみたいと思います。例によって言葉の意味を辞書で調べてみました。お返し(返礼) → 「他人から受けた礼や贈り物に対して、挨拶を返したり品物を贈ったりすること」とあります。ということは、プレゼントをいただいて、どうもありがとうというお礼の言葉を返すこともお返しになるのです。元々何かをしてもらったことに対する感謝の気持ちを表現することがお返しだったのだろうと思います。それが、物質的なものを利用したり、儀式的な要素が入り込むことによって、お返しの意味が変わってきたのだろうと思います。
人に何かをしてもらったり、プレゼントを頂いたときに、相手にお礼の言葉を言うことで自分の感謝の気持ちを表すというだけでは、何となく物足りないように感じるとしたら、それはどんな心の作用なのでしょうか?原因は大きく分けて二つあると思います。一つの理由は、自分が生まれ育った文化の慣習としてのお返しというものが定着しているからというのがあると思います。子どものときから、近所の人から頂き物をしたときに親がお返しを持っていった姿を見慣れていると、それが自然と身についているため、自分が大人になったときにも同じ事をするようになるのです。お中元やお歳暮を頂いたときにも、礼儀として何か品物を贈ることによってお返しをするなどはその典型です。
社会や文化に慣習として定着しているルールを守らないと、人はとても不安を感じてしまうのです。それはおまえはルールを守れない駄目なやつだという自己嫌悪の気持ちと、人から後ろ指をさされるかもしれないという怖れなのです。ある意味世間体を気にして生きることとも繋がります。逆にルールさえ守っていれば、自分は安泰だと思っているのです。それを幸せと混同してしまうこともあるかもしれません。少し考えれば分かることですが、安泰であると思うことと幸せ(心が満ち足りる事)とはまったく別のことです。他人からの評価を下げたくないばっかりに、職場の友人の結婚式に招待されたら、少しぐらい都合が悪かったり、本当は気が進まなくても出席してしまうのです。
初めのお返しの話に戻しますが、お礼の言葉を言うだけでは物足りないと感じるもう一つの理由は、上の例とはまた別の人の心の中にある怖れや不安なのです。そしてそれ自体がそういったお返しの慣習を作る元となったとも考えられるのです。それは一体なんでしょうか?それは相手の好意を真正面から受け取ることに対する怖れではないかと思うのです。そういった怖れが心の中にあると、相手の好意に対して素直な気持ちで喜び、感謝の気持ちで受け止めて自分の中で消化するということができなくなってしまうのです。場合によっては、相手の行為に対してとても恐縮してしまったり、こんなことをしていただいて申し訳ないといった感覚になることもあるかもしれません。それによって自分の感謝の気持ちがありがとうの言葉だけでは相手に充分伝わらないような不安な気持ちになったりするのかもしれません。だからこそ物質的なお返しをしたくなるのです。場合によっては、倍返しなどと言われるように貰った以上のお返しをして安心している人もいるのです。
そういった相手の好意を受け取ることに対する怖れの感情を起こす元となるものは、自分の存在に対する過小評価なのです。つまり、自分は人から親切にされたり好意を向けられたりするに値する存在ではないという感覚なのです。私はこの感覚のことを無価値感と呼んでいます。この無価値感は人によって、あまりにひどい場合には意識できますが、通常は意識できない潜在意識の中に閉じ込められていますので、自分は該当しないと感じる人がほとんどかもしれません。無価値感があると、人は何事につけても何となく自信がなく、相手よりも自分を低く見ている場合があるかもしれません。そして、それをカモフラージュするために、プライドという鎧をつけたり、人を見下すという行為をするようになったりします。
こういった自分の本当の気持ちに気づきたくないために、お礼の言葉だけではいけないというルールを作るのです。そしてルールだからお返しをするのは当然なのだとして、自分の行為を正当化してしまうのです。そのルールこそが義理なのではないかと思うのです。この義理というルールに沿って生きていくことで、他人からとやかく言われる怖れを感じないで生きていけるだけでなく、心の奥に潜む、自分への駄目出しをしている自分に気づかないで生きていけるのです。しかし一方で義理を重んじるために自分の人生を犠牲にしてしまう可能性もあるのです。そして一番問題となるのは、本当の自分を見つめることをせずに誤魔化して毎日を送ってしまうことなのです。そうなると不自由さを感じてもそれをどう変えていけばいいのかが分からなくなってしまうのです。
故人を偲ぶためにお墓参りをしますが、本当に墓地まで行かないとできないことでしょうか?自分の時間と労力を割いて、遠い墓地に墓参りに行く方が達成感があるのは分かりますが、本来は心の中でできることだと思います。一年に一度くらいは顔を見せに帰ってこいと親に言われて帰省しますが、いざ帰っても実家が居心地悪かったりして、それを思うと気が進まない、面倒だと感じながら帰省するのは義理だと気づく必要があります。義理でする親孝行ほど馬鹿げたものはありません。面倒臭くて仕方のない年賀状を毎年イヤイヤ書いて送るのも義理です。そこには充分にお返しをしないではいられない怖れの気持ちと同じものが潜んでいます。
自分の人生に不自由さを感じて何とかしたいと思うのでしたら、一度義理を欠いて生きてみることをお勧めします。勿論できるところからで構いません。きっと心が自由な人ほど、義理を欠いて生きているのではないかと思うのです。なぜなら、心が自由な人は上述したような怖れが少ないため、義理を重んじる理由が自分の中にないからです。そういう人は自分がそうしたいと思うことは、たとえそれが人からみて馬鹿げた事に思われるようなことでもすることができるのです。毎週末墓参りに行こうが、何の記念日でもないけれど大切な人に贈りたいものを送ろうが、自分の魂が喜ぶことであれば何をしてもいいということを腹の底で分かっているのです。
気が進まないこと、体面を気にしてるなと思えるようなこと、仕方なく今までやっていたようなこと、そういった義理でしていたことを止めていくのです。そうやって自分の心の中にある怖れと戦ってみるのです。そうすると、本当は何を怖れていたのかが明確になり、そしてそれが幻想だったということまで気づくことができます。大人の自分は実は何も怖れることはなかったのだと実感するはずです。自分の無価値感に気づいて辛くなってしまうこともあるかもしれませんが、しかしその感情をよくよく見つめてみることで、より深い癒しの糸口をつかむ事もできるのです。