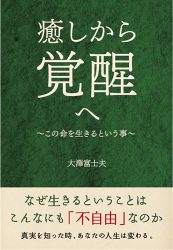小学校の低学年の頃、ある日家に帰ってみると、白くて小さな子犬が家の中にいてびっくりしたことがあります。姉がどこかの知り合いから譲ってもらった犬らしいのですが、それが驚いたことにその子犬が私のことを馬鹿にするような態度をとるのです。生まれてまだ3ヶ月もたたないような子犬なのですが、明らかに自分の方が後からやってきた子どもの私よりも立場が上だと思っているらしいのです。可愛がってあげようと手を出しても、その小さな身体でふてぶてしく反抗してくるのです。
勿論しばらくして犬と私の立場は逆転したのですが、子犬に馬鹿にされたようで子ども心にも多少悔しかった気持ちを覚えています。一般に犬は飼い主の家族同士の上下関係や微妙な人間関係をすばやく察知する能力があると言われますが、我が家に貰われて来たその子犬も家族の中で一番チビだった私を自分よりも下と判断し、見下すような態度をとったのでしょう。今思い返すと笑えるようなことですが、その時はなぜ貰われてきたばかりの子犬がそんな態度をとるのか、全く分かりませんでした。
犬がなぜ敏感に家族の人間関係を感じ取れるのかは分かりません。しかし、犬ができることなら乳幼児期の子どもができないはずはありません。人間の赤ちゃんも、歩いたりしゃべったりできるようになるかなり前の段階から、家族の中にある人間同士の細かな関係を感じ取っているのではないかと思うのです。家族というのは、父母、祖父母、兄弟など以外にも、叔父叔母などの親戚も含めて、一つの家に同居している全員を指します。人数が多くなればなるほど、それだけ人間関係は複雑になる傾向にあると言えます。
日本に古くからある代表的な家長制度では、祖父母が頂点にいて、次に父親、そして長男という順番に続き、嫁に来た母親は自分が産んだ長男よりも位置が低く、女の子どもはみな、母親という女中頭の下にいる女中のような位置付けであったと言えるかもしれません。さすがに今の時代ではこれほどまでにはっきりとした上下関係が家族の中にあることは少なくなってきているでしょうけれども、生まれて家族の一員となった赤ちゃんは、半年、一年と家族と生活を共にしていく間に家族のシステムを自然と学ぶことになるのです。
家族のシステムとは、家族が一つのまとまった塊である機能体として、それを維持管理していくために必要となるメカニズムのことです。それは、家族の構成員同士の上下関係や、家族の構成員一人ひとりの役割などから成り立っているのです。そういった家族のシステムを幼い子どもは敏感に察知して、何とかその中で自分も一人の家族の構成員としての役割を担っていこうとするのです。そして、それは自分以外の家族から期待されるという形で自覚する場合と、子ども自身がみずからある役割を自分に課す場合とがあるようです。そしてその両者がミックスしたような状況も実際には沢山あるのです。
家族の誰かから役割を期待される場合というのは、子どもがある程度の年齢になってからである場合が多いかもしれません。期待というと聞こえはいいですが、実際には利用すると言った方が近いかもしれません。例えば、大家族で母親が家事仕事に追われて忙しい場合などに、兄弟の中で年上の子どもが年下の兄弟の面倒を母親に代わって見させられるということがあります。このように、家族を存続していくためにはある程度仕方なく役割を振り当てられることもあるのですが、理不尽な役割というのもかなりあるのです。例えば、両親の仲が悪くて、お互いに面と向かって口をきこうとしないような場合に、子どもが対話の伝達役として使われるというケースがあります。
また、父親が子どもに自分の意思を直接伝える代わりに、母親を利用して間接的に叱らせたりすることもあります。この場合には母親が伝達者としての役割をさせられていることになります。母親が父親や舅、姑などとの人間関係がよくない場合などに、ある特定の子どもにその悪口を毎日のように言って聞かすような場合もありますが、その子どもは愚痴の聞き役という役目を果たすことになってしまいます。このように、家族の一人ひとりの精神的な問題が原因となる人間関係の悪化をカバーして、家族を崩壊させないようにするために、何かの役割を割り当てられるという場合がとても多いのです。
こうして割り当てられた理不尽な役割を果たしていくということは、本人にとって決して心地いいものではありません。しかし、家族というかけがえのないものを守っていくためには、そう簡単には期待された役割を自分から降板することはできないのです。そのために、本人は知らず知らずのうちに自分を苦しめ我慢をする生活を続けていってしまうことになるのです。そして、もう一つの場合、つまり子ども自らが何かの役割を自分に課してしまう場合には、更に強烈な我慢をして自己犠牲を強いる毎日を送ることになる傾向が強くなるのです。
例えば、激昂しやす父親が年上の兄弟を叱る場面を何度も見ている子どもは、父親を決して怒らせないように振舞うようになるのです。それは誰からも期待されたわけでもないのに、自分から進んで父親の感情を高ぶらせない役割を果たそうとするのです。この場合には基本的な自己表現ができなくなるので、多くの感情を溜め込むことになるかもしれません。また母親と姑の仲があまりよくないことを察知した赤ちゃんが、自分が一緒にいると二人の関係が丸く収まることを知って、自ら仲介役となって何とか関係が悪くならないように役割を果たそうとするのです。自分が家族の潤滑油だと自覚している幼い子どもはとても多くいるのではないかと思います。
このように自発的に役割を担う子どもの心理というのは、不安や怖れが基となっているのです。自分が親からしっかりと愛されているという感覚が薄い場合には特にこの傾向が強くなり、大切な家族が壊れてしまったらどうしようという不安感から家族の調整役をかってでたりすることになるのです。このような役割というのは、子どもに限らず大人でも自発的に持ってしまうことがとても多いのです。それは何かを守るためだったり、結局は怖れを回避しようとする心の状態なのだと言えます。しかしそのために思ってもみなかったような多くの犠牲を自らが被ることになってしまう可能性が高いのです。
家族のシステムというのは特別なものではなく、家族に限らず人が何人か集まった場合には、そこになんらかのシステムが必ず発生してくるのです。そして家族の場合と同じように、構成員のそれぞれが何らかの役割を担うことになります。会社などのように初めから目的が決まっている組織のような場合には、役割がはっきりと決まっているし、そうでなければならないのですが、問題となるのは家族にしてもその他の組織にしても自発的に役割を作ってそれを果たそうと頑張ってしまうような場合なのです。
生まれ育った家族の中で、自発的に何らかの役割を果たしてきてしまった人は、大人になって別の組織の中に入ったときに、同じような役割を自分に背負わせることになってしまう傾向がとても高いのです。自分が所属している家族やグループ、その他の組織などにおいて、何らかの役割を自分に課していないかどうか、そしてそのために自分は我慢して自己犠牲を強いてしまっていないかどうか、よく考えて見直してみることです。それは自分以外の人から、何らかの理不尽な役割を押し付けられてる場合も同じなのです。
そして、本当はいつでもその役割を手放すことができるということを知ることです。一人の人間としてのあなたは、本来役割などというものは持つ必要はないのだということにしっかりと気付くことが大切なのです。そのことが分かるだけでもとても楽になります。そして、余分な役割をできるだけ手放すことができた人ほど、人に役割を期待することが少なくなるのです。そうなればなるほど、不満を感じることが少なくなり、逆に満たされた心で毎日を送ることができるようになっていくのです。