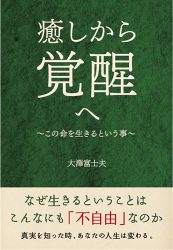私たち人間は、日々人間関係という大海原の中を泳ぎながら生きていると言ってもいいくらい、様々な局面で自分と他人の関係を築きながら生活しています。気持ちのいい人間関係を作っている人もいれば、なんだかうまくいってないと感じてる人もいます。その違いは何なのでしょうか?そもそも人間関係がうまくいくとはどういう状態のことを指すのでしょうか?人間関係を築いていくのに必要不可欠なものはコミュニケーションであることは誰しも理解しているのですが、ではいい人間関係を作っていくための良好なコミュニケーションとはどんなものなのでしょうか?
人と人がコミュニケーションをとろうとするときに、最も多く使われる手段は言葉であると思われがちですが、実は言葉によるコミュニケーションというのは、コミュニケーション全体の数十パーセントでしかないということが実験によって分かっています。つまり、人はコミュニケーションの多くを言葉以外の何らかの手段によって実現しているということです。例えば、相手の表情であったり、しぐさだったり、口調だったりということです。自分も身振り手振りを使ったり、やはり表情や態度で自分の真意を相手に伝えようとします。
それ以外にも、人間は人の気(エネルギー)のようなものを感じることもできるかもしれません。何かを感じて後を振り返ったらじっと見られていたとか、何か殺気のようなものを感じたり、大勢の人がいるところに行くだけで、気持ちが悪くなってしまったりすることがあります。こういうエネルギーのようなものもコミュニケーションの手段として無意識のうちに使用しているということもあるかもしれません。例えば今相手が怒っているということは、相手の表情や口調から容易に察することができますが、腹の底に怒りを溜め込んでいる人と一緒にいると、その人が何も怒っていないときにでも、何となく怖い感じがするなどはそのエネルギーを感じているのかもしれません。
人間関係の基盤であるコミュニケーションを良好にするには、上記したような能力をフル活用することで相手の気持ちや考えを分かろうとする、あるいは理解することがとても大切なことなのです。それなしには、どんなに賢い人が二人揃っていて、いくら長い時間をかけて議論したところで、理想的なコミュニケーションをとることは難しくなります。それは一方通行をお互いに繰り返すだけになってしまうからです。では、誰もが持っているそのような自分以外の人の気持ちを感じ取る力、あるいは汲み取る能力というのは、一体何歳ごろからどうやって人は身に着けるようになるのでしょうか?
最近急激に発達してきた乳幼児の精神医学や脳科学の分野の研究成果などから、どうも人は生まれながらにそういう能力を身に着けているらしいということが分かってきています。生まれたばかりの赤ちゃんは、言葉を使えないかわりに、泣いたりむずったりすることで自己表現をして、自分の意志や気持ちを親に伝えようとします。しかし、赤ちゃんがしていることはそれだけではなく、いつも一緒にいて自分の面倒を見てくれているお母さんの気持ちを分かろうと最大限の努力をしているのです。なぜなら、それが自分の命にかかわる最重要事項だからです。その時に使うのが上記の能力なのです。誰から教わることもないのに、赤ちゃんにはそれができるのです。
つまり赤ちゃんにとってはお母さんとの良好なコミュニケーションというのは自分の命にかかわる大切なものなのです。赤ちゃんが訴えた信号をお母さんが速やかにキャッチして、赤ちゃんの期待通りの反応を返してくれたら赤ちゃんは安心することができますが、その逆にいくら信号を送ってもお母さんがその真意を気付けずにいたら、赤ちゃんはとても不安になってしまうのです。これが人生で最初のコミュニケーションの失敗、つまり人間関係がうまくいかない状態なのです。その不安を解消するために、赤ちゃんは必死になってお母さんの心の中を読もうと努力します。少しでもお母さんの気持ちを察してお母さんにとって都合のいい子になれば、自分の気持ちが伝わるのではないかと思うからです。
ここで赤ちゃんは全精力を使ってお母さんを理解しようとして、今までのお母さんの反応をすべてデータベース化していくのです。つまり、お母さんがこの表情のときに自分が泣くとお母さんはこうなるとか、お母さんがこんな感じになっているときには、自分はこうした方が無難だろうなどのように、お母さんの状態とそれに見合った自分の反応をルール化していくということです。それによって、前もって不安を感じることをできるだけ減らしていこうとするのです。勿論その時々のお母さんの心の中を読み取るときに使うのが、上述した人が生まれながらに持っている読心能力なのです。
ところが、不安感が強い傾向にある赤ちゃんは、自分で作ったデータベースに頼りすぎてしまい、実際のその時々のお母さんの行動を先読みするようになります。それが功を奏して、赤ちゃんは自分が受けるダメージを最小限にすることができるのですが、ここには大きな弊害が二つあります。ひとつは、コミュニケーションが不足しても構わなくなっていくことです。赤ちゃんは次第にお母さんの心の状態と自分のデータベースだけを見ることで、不安から逃れようとするようになるのです。結果として、自己表現をしない赤ちゃんが出来上がってしまいます。
そしてもう一つの大きな問題は、時が流れて赤ちゃんが成長して、子どもから大人になっていっても、幼いころに作ったデータベースをいつまでも参照してしまうため、実際のお母さんが以前とは違う行動をするようになっても自分の反応を変えることができなくなってしまうのです。これが独りよがりなのです。独りよがりな人というのをイメージすると、何となく強欲な自分勝手な人を想像するかもしれませんが、例によって、『独りよがり』について辞書で調べてみると、『自分ひとりだけでよいと決め込んで、他人の考えを全く聞こうとしない・こと(さま)。』とあります。
つまり、独りよがりというのは、幼い頃の不安や怖れを回避するために作った過去のルールを優先して、現実の相手の反応を見なくなってしまった人のことを言うのです。忙しそうにしているお母さんに声をかけたら、きっとお母さんは面倒くさそうな顔をするに決まっている。幼い頃に作ったこのルールを尊重し続けてしまうと、もしかしたら現在のお母さんはいつも面倒くさそうな態度をするわけではないかもしれないのですが、それを見極めようともしなくなって、結局忙しそうなお母さんには話しかけられない状態が続いてしまうということです。
更に、人は過去にお母さんやお父さんに対して作ったデータベースを、他の家族やそれ以外の他人にも流用するようになっていきます。忙しそうなお母さんに声をかけたら面倒くさそうな顔をされるというルールを他の人にも適用してしまうと、職場などで忙しそうな人には声をかけ辛い大人になってしまいます。しかし仕事上では、どんなに忙しそうな人にでも言うべきことは言わなければ逆に問題にもなってしまうかもしれません。一言自分の気持ちを伝えると、お母さんはいやというほど根掘り葉掘り質問をしてきて辛いという過去のルールを他人にも適用してしまうと、自己表現を異常なほど怖れる人になってしまうかもしれません。実際には周りの誰もしつこく聞いてくるようなことはないというのに。
そして実は独りよがりを作り上げてしまう理由のもう一つの大きな原因があるのです。それは、自分が持っている相手の気持ちを汲み取る能力、読心力を過信してしまうということなのです。あなたは絶対怒っているに違いない、あの人がこういう態度をとるときにはきっとこう思っているはずだ、などのように勝手に決め付けてしまうのです。しかし、よくよく考えてみると、生まれながらの能力はあるとしても、それがいつも間違いなく機能しているかどうかの保証はないのです。もっとはっきり言えば、人と自分は本来別々の個体なのです。従って、人は自分以外の人の気持ちは本質的には分かりようがないということをしっかりと気づく必要があります。単に類推することができるというだけなのです。そしてだからこそ、なるべく相手の気持ちを分かろうと努力することが大切なのだとも言えるのです。
自分が過去に作ったデータベースによって相手の反応を先読みしてしまうことと、読心力を過信して相手の気持ちを決め付けてしまうことの両方が揃ったら、それこそ完璧な独りよがりな人間が出来上がることになるのです。それは例えて言えば、相手と自分の間に勝手な相手の像をこしらえて、その虚像のほうばかりをいつも見ているようなものなのです。だから、本物の相手がその像と食い違う言動をしてもなかなか気づかないし、いつも一緒にいても本当には心が通じ合うことができなくなってしまうのです。言葉の通じない異国の人と通訳を介してコミュニケーションするとき、相手の方を見ないで通訳の人の方ばかりを見てしまうことがよくありますが、その通訳の人が自分が作ったデータベースを元にした相手の虚像だと思えば分かりやすいかもしれません。
独りよがりを止められないと、円滑なコミュニケーションができなくなるだけではなく、人生の様々な場面で損をしてしまうことも多くなるかもしれません。たとえば、子どものときに、習い事を辞めたいと親に言ったら、親がとてもいやな反応をしたというルールを使い続けていると、大人になって退職したいという意思を上司に言えないという状況になってしまうかもしれません。上司の気持ちを悪くするかもという独りよがりをしてしまうのです。また、勉強ができると親が喜ぶというルールを使い続けていると、頑張って勉強をして学校の先生に喜んでもらおうとするかもしれません。先生の質問には何でも答えられるように予習してしまうと、もしかしたら質問に答えられないことを期待している先生から敬遠されてしまうかもしれません。答えられない生徒がいればこそ、先生が教えるということに意味がでてくるからです。
人間関係に自信がある人でもない人でも、一度自分は独りよがりをしていないかよく点検してみて下さい。自分はどうも人と比べて不安感や怖れが強いかもと感じている人は、独りよがりを人一倍してる可能性が高いのです。それは不安や怖れが多い人ほど、何事も決め付ける傾向が強くなるからです。実際独りよがりを全くしていない人というのはいないのではないかと思います。もし、自分がしている独りよがりに気がついたら、人間関係や人生をよりよいものに変えていく絶好のチャンスです。それが読心力の過信からくるものか、データベースを優先する先読みからくるものなのか、しっかり見つめてそれらのものを一つひとつ手放していくことが大切なのです。