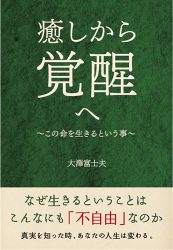コラムの『恋愛は心の窓』の中で、「好き」の正体は、「愛」と「依存」であるというお話をしました。「愛」か「依存」のどちらか一方だけというよりは、両者が混ざり合っていて、より幸せになるためには「好き」の中の「愛」の割合を増やしていく必要があるとも書きました。「愛」と「依存」の違いを要約すると、「愛」は対象となる存在そのものに対して向けられるものですが、「依存」は存在の属性に対して向けられるのです。
今までコラムを読み進んで来られた方は、この意味が分かるのではないでしょうか?「愛」は相手の存在をすべての感覚で感じて、繰り返し味わうことで得られる愛しさだったり、大切と思う心なのです。一方、「依存」は、幼少期に残してきた満たされることのなかった依存心の再現なのです。従って相手が自分にとって都合のいい属性を持っていてもらわないと困ることになってしまいます。成人した人が特に気にする相手の属性というのは、家柄だったり、社会的な地位、財産や学歴、その人の能力あるいは容姿だったりするのです。
依存という言葉が何となくそぐわないのであれば、存在意義と言う言葉で考えてみたらどうでしょうか?存在意義というのは、その存在が自分にとって必要とするものであったり、利用価値のあるものの場合に発生するものです。これは、左脳で考えて論理的にも決めることができるものです。これに対して存在価値は、頭で思考して決めることはできません。なぜなら存在価値は心で感じるものだからです。
愛する我が子が何か大変な犯罪を犯してしまったと仮定します。その時に親である自分は子どもの存在に対してどのような心の変化があるでしょうか?もしも、子どもを愛しく思う気持ちが半減するかもしれないと思うのでしたら、それは子どもの存在意義を感じて生きているということです。つまりそれは、依存がベースにあるということです。しかし、子どもを大切に感じる気持ちが何も変わらないというのでしたら、子どもの存在価値を感じられていることになります。つまり子どもへの愛がベースにあるということです。
小学生のときに、『罪を憎んで人を怨まず』という言葉が好きでした。こんな言葉が本当にあるのかどうか、正確を期そうと思い今ネットで調べたところ、多分これがキリスト教の言葉らしいということが分かりました。怖ろしいですね、40年間も知らずにいたなんて。なぜこの言葉が幼い心に残っていたのかは分かりません。教科書に載っていたものか、どこかの大人から聞いた言葉だったのか今となっては定かではありません。しかし、今思うとこの言葉には、愛、つまり存在価値のことがうたってあるのです。人のした行為には、憎むようなことがあっても、それをした人そのものの存在価値は変わらないと言っているのです。
幼い子どもがお母さんに褒められて、お母さんに抱きしめられて、「お母さん大好き」と言うかもしれません。しかし、一方でお母さんに叱られた時には、「お母さんなんか大嫌い」と泣いて叫ぶかもしれません。一体どっちなの?とお母さんが子どもに向かって皮肉を言うかもしれませんね。子どもにとってはどちらも本音です。子どもの言葉をもっと正確に言うと、お母さんという存在は大好きだけど、お母さんが私を叱るという行為は大嫌いということなのです。これを混同してしまって、お母さんという存在に自分の怒りを向けてしまうのです。このことは、何も幼い子どもばかりがやっていることではありません。大人の我々も日常的に全く同じようにして、混同して気づかないまま生きているのです。それを気づかせてくれる言葉が、『罪を憎んで人を怨まず』だったのかもしれません。
愛をもって相手の存在価値に気づいて生きていける人は幸せです。なぜなら相手の行為や属性などに自分の気持ちが惑わされたりすることがないからです。もしも自分が、依存によって相手の存在意義しか分からない状態になってるとしたら、どうしたらいいのでしょうか?それにはどうしてそのような心の状態になってしまったのかを考えなければなりません。実は相手をどう捉えるかというのは、自分をどう見ているのかということから決まるのです。つまり自分の存在価値に気づけないでいる人が、代わりとして自分の存在意義を求めて生きている結果、相手の存在価値にも気づかなくなるということなのです。
自分の存在価値に気づかないまま生きている人にとっては、存在価値と存在意義の区別がつかない場合が多いかもしれません。そのために、自分で自分の存在価値を主観的に決めることはできないはずだ、つまり存在価値は相対的なものでしかないと考えてしまうのです。自分の存在価値は、あたかも存在意義のように、他者から自分の能力やその他の属性を認められるということでしか測ることができないと思ってしまうのです。これはとても悲しいことです。なぜなら、自分がただここに存在していてもいいんだという確信が自分の中にはないということを意味するからです。
そんな辛い心の状態を味わいながら生きていくことはとても無理なので、何とかして自分の属性である人から見た自分の存在意義をできるだけ増やしていこうと努力します。それはたとえば、子どものときには、親から喜んでもらえるいい子になろうとすることから始まります。集団生活に入ると、勉強していい成績をとって、人からの評価を高くしようと努力するのです。思春期以降になると、親切で、道徳心のある善良な人間になろうとします。社会に出ると、評判のいい会社に入ってできるだけ出世して他人から抜きん出ようとするかもしれません。仕事で成果をあげて、周りの人からの高い評価を得るよう努めるのです。しかし、そういうことをいくら積み重ねていっても、結局他人から見た自分の存在意義が、自分の存在価値になるわけではないため、この不毛な努力は永久に続くのです。
こういった心の状態(無価値感)というのは、幼少期からずっと親が共感的態度で接してくれていたかどうかに大きくかかっているのです。コラムの『共感ということ』にも書いたように、親子の会話が少なかったり、批判的な態度の親に育てられてしまうと、自分はこれでいいのだという感覚が分からないまま大人になっていってしまう可能性が大きくなります。もしも、自分の存在価値にはっきり気づいているという自信がないという場合には、どんな方法を使ってでも自分を癒していかなければ満ち足りた人生を送ることは難しくなってしまいます。
自分の存在価値は作るものではなく、元々動物の本能として人間が持っているものだと思っています。ただ幼い自分ひとりでは気づくことができないので、親の助けを借りて自分の成長と共に育てていくものだと思います。存在価値に気づくということは、自分を愛しいと感じる心、大切な存在と思えること、そして自分を危険から守り、いたわってより幸せにしてあげようとする原動力となるのではないかと思うのです。逆に自分の存在価値に気づかずにいると、自己嫌悪や自責の念によって自らを傷つけるような行動をとってしまうことにも繋がるのです。すべての人に自分の存在価値をはっきりと気づいて欲しいと願ってしまいます。なぜならそれが一人一人が幸せに生きられる根幹を成すと言えるからです。