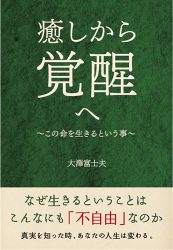私たちは一人ひとり違う個人として生きています。それは人生の目的や夢、物の考え方や好みがそれぞれに違うということだけではなく、別々の個体であるということです。どんなに生き方や趣味が同じであっても、また一緒に生活をしたり、仲良く会話を楽しむことができても、そのことはそれぞれの個人が一体になることではありません。よく、とても親密な恋人同士が私たちは一心同体だと言って仲のよさをアピールすることがありますが、そこには時として大きな問題が隠されている可能性があるのです。
その問題とは何かというと、自分と相手との間に適切な境界線を作れない、あるいは作れていないことに対する自覚がないということです。では境界とはいったい何でしょうか?境界があるとは、境界がないとはどういうことを意味するのでしょうか?人と人との間に適切な境界が作れていない場合に、どういう問題が起きてくるのかということを見ていくことで、境界とはどんなものか、境界がどれだけ大切なものかということを考えていくことにします。
AさんとBさんが隣り合わせの家で暮らしているとします。この二人は以前からとても仲がよく、互いに気心も知れあった親戚以上の付き合いをしていました。ある日Aさんは自分の家を囲んでいる柵を大好きな緑色のペンキで塗ってみました。すべての柵を塗るのはとても骨の折れる作業でしたが、出来上がった柵を見てとても気に入ってしまい、隣のBさんの家の柵も古くなってペンキが剥げているのを見て、Bさんが留守の間に親切心を働かせて同じ緑のペンキで塗ってあげました。苦労の甲斐あってか、隣接する二軒が同じ緑色の柵で囲まれている様は、Aさんの期待以上の見栄えとなりました。さぞBさんも喜んでくれるだろうと、Bさんの帰りを待っていました。
そこへ帰ってきたBさんは柵を見てびっくりしました。実はBさんも自宅の柵のペンキが剥げてきていることに気づいていて、近々大好きな赤色のペンキを塗って、買ったばかりの赤のスポーツカーと同じ色にしようと計画していたんです。緑色に塗ってしまったのがAさんであることは明白です。買っておいた赤のペンキも無駄になってしまいました。落胆していると、事の顛末をAさんが来て話し始めました。Aさんは満面の笑みでどんなにきれいな出来栄えになったかを話しています。BさんはすぐにAさんの好意に気づいて、落胆していることや赤で塗ろうとしていたことを隠し、笑顔を作って感謝の意を伝えました。
Bさんはその晩、ひとりになって自分の気持ちを見つめてみました。何かおかしい、このもやもやとした感覚は以前にも感じたことがある。それも何度も。Bさんが初めに思い出したのは、Aさんと知り合ってまもなくの頃のことでした。Aさんはお近づきのしるしにと言って、Aさん宅に夕食を誘ってくれたのでした。Aさんは料理が得意らしく、何品もおいしい料理を作ってもてなしてくれました。Bさんはお腹がいっぱいになるまでご馳走を頂きました。Bさんがもう満腹です、おいしい料理をご馳走様とお礼を言うと、Aさんはとても喜んで、これも食べて欲しい、あれも食べて欲しいと更に次々と料理を運んできます。Bさんはもうこれが限界というところまで無理して食べた後、帰宅して具合が悪くなっていたのでした。その後もAさんに夕食をご馳走になるたびに、Bさんはひどく食べすぎて体調をくずしてしまったことを思い出したのです。
またこんなことも思い出しました。旅行が大好きなAさんは、旅行に行くたびにBさんにおみあげを買ってきてくれるのです。それは大抵が決まってAさんの家にも置いてあるような置物だったのです。Bさんもなかなか趣味のいいその置物を気に入って初めのうちはとても喜んでいました。ところがそれが繰り返されていくうちに、もともと部屋をすっきりさせておきたいBさんは、次第に増えていくその置物が邪魔に感じ始めました。Aさんに毎回おみあげを頂くのも申し訳ないといって断ったのですが、Aさんは今だにそのおみあげを買ってくることをやめません。Aさんの好意を思うと、Bさんはそれ以上のことを言えなくなっていたのです。
こんなこともありました。Aさんは仕事から遅く帰ってきたときに限って、Bさんに電話をかけてきて、職場での悩みや愚痴を話すのです。日頃から面倒見のいいAさんに何かと世話になっているBさんは、その話を親身になって聞いてあげるうちに、気がつくとすぐに1時間も2時間もたってしまって、ようやく電話を切ったときにはいつもどこかぐったりと疲れてしまって、次の朝起きるのが辛いということが何度もあったのです。電話がかかってくるたびに、今日は早く切ろうと思うのですが、どうしても言い出せずに最後まで付き合ってしまうのです。
ここまで思い出したBさんは、はたと気づきました。自分はAさんに侵略されているということを。そして自分もそれを許してしまっているということを。なぜ今までこんな単純なことに気づかないできてしまったのか?いや、よく考えてみると、きっとどこかで気づいていたはずだけど、それを考えないようにしてAさんとの人間関係を保とうとしてきたのだということにも気づいたのです。
もうお分かりのように、AさんはBさんとの間の境界が曖昧であるために、よかれと思って好意でしていることがBさんを侵略してしまっていることに気づいていません。BさんはAさんとの間の適切な境界が作れていないために、『ノー』が言えないお付き合いをして侵略を許してしまったのです。このように境界が分からない人たちは、境界を越えて相手を侵略する侵略者になったり、侵略を許してしまう被侵略者になったりするのです。本人同士がうまくいってるうちはいいのですが、一般的には侵略されてる側の人が自分の本当の苦しさに気づくことで、関係は解消されたりすることになってしまいます。
ではなぜAさんやBさんは境界が分からずに、相手を侵略したり、侵略されたりしてしまうのでしょうか?その答えはその人たちの幼少期から青年期くらいまでにあります。つまり親にどのように育てられたかに原因があるのです。境界の分からない親に育てられると、侵略を受けてしまうために適切な境界を作ることを妨害されてしまい、結果として境界の分からない人物になってしまう可能性が高いのです。では境界の分からない親はどんな育て方、あるいは接し方をするのでしょうか?代表的な事例を挙げてみていくことにします。
例えば父親が自分の信念なり主張などを、躾けと称して子どもに押し付けることがあります。父親自身が人はこうあるべき、これが物事の正しい考え方だというようなことを思ったり言ったりするだけであれば、何も問題はありません。問題はそれを子どもに押し付け、強要することです。これが侵略になるのです。親は子どもにとって、絶対的な力を持っていますから、いとも簡単に侵略することができてしまうのです。例えば、威圧的な態度で言うことを聞かす、言うことを聞かない場合には体罰を与えるなどです。子どもは怒られる恐怖や、あるいは親に逆らうことの罪悪感などから『ノー』が言えなくなるのです。
たとえば門限を設定して、厳重に監視してそれを守らせるといったことです。門限を作ること自体が悪いのではなく、何が何でもそれを守らせる押し付けが問題なのです。子どもが適当に門限を破ったりできる場合には、行動で『ノー』を表していることになるので、それなりに境界を作ってることになるので比較的軽傷で済みます。逆に、どんな状況下でも必ず門限を守ってしまう子どもの場合には、知らず知らずのうちに親の侵略を受けて、境界を作れない人になってしまいます。
このように言われると、親は子どもを正しい方向に導く義務がある。少なくとも、子どもが成人するまでは、子どもを危険から守り保護する義務があると主張される方もおられるでしょう。しかし、門限をたった10分や15分でも守れなかった子どもを叱る親は、自分が子どものために怒っているのではないことに気づきません。親は自分の思い通りに行動しない子どもに腹を立てているのです。あまりに早い時間に門限を設定する親の場合には、子どもの安全のことよりも自分が心配することを避けたいために門限を設定するのです。心配性というのは、境界の分からない人の代表的な特性です。
真に親がすべきことは、親が正しいと思う方向に導くのではなく、子ども自身が自分で何が正しいかを見出せるようにしてあげることです。親の心配から子どもを守るのではなく、子ども自身が自分の身を守る能力を身につけられるようにしてあげることなのです。境界の分からない親はこの違いが曖昧なのです。こういう親は、子どもが成長してくると、「もうお前もそろそろ大人なのだから、自分の足で自由に生きていきなさい。」などともっともらしいことを言ったりしますが、今までずっと長い間侵略され続けてきた子どもは、どうやって生きていけばいいのか分からなくなっているのです。他人と自分の間に境界を作ることがうまくできなくなってしまっているので、対人関係で悩んでしまう場合もあります。そして自分が何者なのかも分からくなってしまうかもしれません。仕方なく、親から洗脳された親の信念を抱いて、うその自分の人生を生きていかなければならなくなってしまいます。
もう一つ、今度は境界の分からない母親の典型的な例を見てみます。母親が可愛い我が子に幸せになって欲しいと願うのは当然ですが、無意識のうちに自分の幸福感を子どもに押し付けてしまうのです。勉強を強要して、この学校に入って、この仕事をして、こんな人と結婚するとあなたは幸せになるという具合に押し付けるのです。侵略者となった母親は自分の思い通りに子どもを行動させるために、意識的にも無意識的にもあらゆる手段を使ってきます。子どもはその手口に簡単にやられてしまうのです。学校のテストで期待通りの点数がとれると喜ぶ反面、少しでも期待通りではないときには、怒ったり、嘆き悲しんだりするのです。これを繰り返されていくうちに、子どもは自然に飼いならされて行きます。そして、母親の意向に沿った人生を歩むことに慣れていってしまいます。
何故こうなるかというと、境界が分からないために、母親自身の人生と子どもの人生を区別することができないからです。このような母親は自分の周囲に適切な境界がないために、自己というものが曖昧であることから世間体重視の人生を歩んでいる傾向が強いのです。その生き方も含めて子どもに押し付けてきます。そして、いつまでも子離れできない面倒な母親をずっと演じることになります。必要以上に子どものことを心配する、そして過保護になり、執拗に子どもの生活に干渉してくる、子どもを溺愛する母親になるのです。子どもがいない間に机の中を調べたり、嫌いな食べ物でも食べるように強要したり、着せてかわいいと思う洋服を着せて自分が喜んだりしているのです。
弱い立場の子どもは母親に愛されたいといつも強く望んでいるために、母親が侵略してきてもそれを受け入れようと健気に努力してしまいます。母親の望むような自分になろうと必死になります。本当の自分は母親が望むような存在ではないということにも気づいていて、そんな自分を責めてしまいます。そして本当の自分は母親から愛されない、見捨てられてしまうかもしれない存在だと思うのです。子どもにとって、親に見捨てられるということは死ぬことを意味しますので、命がけの恐怖を感じます。だからこそ命がけで親に気に入られる自分になるために頑張るのです。それが大切な境界を作っていく作業を真っ向から妨害させてしまうのです。親に『ノー』と言えない、素直な自己表現ができなくなる理由はここにあります。
人は子どものときの親との対人関係をベースに他人との対人関係を作っていきます。そのために、境界の分からない親に侵略され続けて育った人は、大人になっても境界が曖昧なままの対人関係を作り続けることになるのです。前述のAさんのように侵略者になるか、Bさんのように被侵略者になるかは、育てられ方や本人の気質によって変わってきます。あまりにも強大な侵略者の親に育てられると、どうしても被侵略者の傾向が強くなってしまいます。また積極的なタイプと消極的なタイプ、あるいは外交的か内向的かなどの気質にもよるところが大です。しかし、それだけではなく、自分と相手の立場の違い、力関係などに拠ってダイナミックに決まってくることも多いのです。職場の上司と部下、先輩と後輩、夫と妻、先生と生徒、そして親と子など、いくらでも侵略者、被侵略者のできる関係が存在します。Bさんは、Aさんとの関係においては侵略されてしまっていますが、親になったあかつきには、侵略者となって子どもを育てる可能性が高いのです。
ここまで読んできて、自分はもしかしたら境界が分からない人なのかも知れないと感じた方もおられるかも知れませんし、あるいは自分は大丈夫だと思った方もおられるでしょう。いずれにしても、以下に境界の分からない人たちの代表的な特徴を挙げてみますので、自分が該当するものはないかどうかチェックしてみてください。
-相手に『ノー』と言うのを難しく感じて、つい承諾してしまう
-人は人、自分は自分と簡単に割り切れない
-自分のために生きていると心の底から断言できない
-人の視線、顔色、態度などがとても気になってしまう
-人のちょっとした言葉にすごく反応してしまうことがある
-人の役に立ちたいといつも思っている
-頑張れば人を幸せにできると思っている
-子どもに対して過干渉、過保護、溺愛してしまう
-自分というものが分からない
-人やものに依存しないではいられない
-人が自分から離れていくことにとても恐怖を感じる
-何となく自分に自信がない
-とてもプライドが高い
-「~ねばならない」、「~あるべき」が強い
-世間体を重視する
-善悪、正不正、白黒はっきりつけたい、曖昧さを嫌う
一つでも二つでも該当するものがある場合には、境界が分からないか、境界があやふやな傾向にあると思ってください。境界は単純に分かる、分からないというものではありません。境界が分からない傾向が強ければ強いほど生きづらくなりますので、沢山該当するものがある場合には、真剣に境界を作っていくことに取り組んでいく必要があると思われます。こういった特徴は実際にはいくら挙げてもきりがないのです。それは、境界が分からないで生きていることそのものが、あらゆる人の苦しみや不幸の元だからです。
だいぶ前に「ノーと言えない日本人」という本がベストセラーになったことがありました。日本人は昔から境界が曖昧な文化の中で生きているとも言えます。結婚式で花嫁さんが着る白無垢というのがありますが、あれは、真っ白い状態で嫁いで、ご主人様の好きなどんな色にでも染まるようにという意味が込められているらしいです。美しい白無垢を身にまとうことが悪いことなのではありません。この境界の分からない心の状態のままでは、花嫁さんも花婿さんも幸せになるのは難しいということです。
境界が分からない人は、自分と相手とが癒着している状態で生きています。自分の周りぐるりと360度適切な境界を作って、その内側が自分なのですが、境界がなければ内側も外側もないので、はっきりとした自分というものが持てなくなってしまうのです。これでは自分が何者なのかはっきりつかめないままで人生を送ることになります。境界があるからこそ、人の侵略から大切な自分を守ることができるし、境界を越えて人を侵略することもなくなります。対人関係において、境界から内側だけに責任を持てばいいのです。境界の向こう側に責任を持とうとすると、そこから侵略が始まるのです。そうなると、境界の外側にも自分のエネルギーが流れていくので、大変な消耗をしてしまうのです。
では境界の内側に責任を持つとはどういうことでしょうか?それは、侵略されてしまった自分ではない、本当の自分の声にしたがって生きること。自分は本当は何をしたいのか、その望みをかなえてあげること、望まないことは避けてあげること。自分にうそをつかない生き方をすることなんです。コラムの『幸せになるための三つの方法①』に書いてあるように、我慢や無理をしないということなのです。逆の言い方をすれば、こういった生き方ができるようになっていくことで、適切な境界が作られていくとも言えます。
そしてもう一つ大切なことは、自分が境界を作ることを妨害しているものは何かをよく見つめてみることです。そこには必ず怖れの感情があるはずです。その怖れとは、幼いときに親から離れていかなければならない不安感、親に愛されずに見捨てられて死んでしまうかもしれないという激しい恐怖感なのです。その感情は形を変えて様々なマイナスの感情となって子どものときに溜めてきてしまったのです。怒りや悲しみや寂しさ、そして自己嫌悪や罪悪感などがその怖れとともに沢山心の奥に沈殿しているのです。その感情をよく見つめて、味わって開放してあげることが大切です。それを繰り返しながら、その感情が小さくなっていくことで、境界を作ることが簡単にできるようになってくるはずです。
最後に、境界を作るということは、決して温かみのない冷たい人になってしまうということではありません。どうしても境界という言葉から、人と人を分け隔てする、自己中心的な人を連想してしまうかもしれません。人類みな兄弟とか、家族の絆、などという感覚から遠ざかるイメージを持たれてしまうかもしれません。実際にはその逆なのです。境界を持てない人は、他人の侵略から自分を守るものがないために、いつも怯えています。そのために、自分自身に分厚い鎧を着せて生活することになります。これは決して本心を明かさない、相手に打ち解けない感じを与えてしまうでしょう。境界を持っている人は、それが自動的に自分を守ってくれるので、丸裸でリラックスして人と接することができるために、とてもオープンな雰囲気を感じさせるかもしれません。
適切な境界を作って、自己を確立することで人は幸せになっていくのです。その人の幸せは、その人の境界の中にのみあるのです。境界の外には決してありません。そして自分が幸せでなければ、本当には相手を暖かい目で見ることはむずかしいのです。コラムの『共感ということ』に共感の大切さを書きましたが、人との境界が分かる幸せな人でなければ、共感することはむずかしいのです。そして高度なレベルにまで境界を進化させられた人とは、どんなに相手にののしられたり、否定されても、それは境界の向こうで起きていることだということが分かるために、自分を責めることもないし、相手に対する怒りや悲しみの感情に揺り動かされることもないのです。