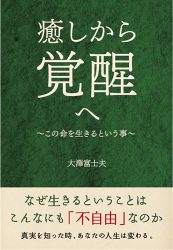osho は、人を三種類に分類できるというのです。一つ目は、見られる対象になってしまう人たち。つまりは演技者のこと。
二つ目は、傍観者になる人たち。そして、三番目は、観察者になる人たち。演技者になる時、その人は一個の物となってしまうのだと。
彼らの努力はすべて、人々を印象付けることにあり、どうすれば良く見えるか、どうすれば美しく見えるか、どうすれば最も良く見えるか、つまりは最善を装う努力だけをする。
対象物になる人は、偽善者となる。彼らは自分の顔を仮面で覆う。外見は善良に見せかけていても内側は…。
二番目の傍観者になる人たちは、膨大な群衆になる。何時間もテレビの前に座る。生きるということが、外側を見ることに費やされてしまう。
この眺め続ける人々は世界中に溢れていて、一つ目の演技者たちはこの傍観者たちを利用することになるのだと。
この傍観者とは、その目が他者に向いているのに対して、三番目の観察者とは、その目が自分自身に向いている者のことなのだと。
この違いは革命的であり、まさに根本的なことなのだと。視界から全ての対象が去り、あなたが、あなただけがいる。
気づきだけが残り、油断のなさだけが残る。この時、あなたは観察者であると。結局はこの観察者でいる時にのみ、自己の本質に気づくことができるのだと
私なりに補足すると、この純粋な気づきだけが現れとなって初めて、全ての実体が消えていくのだろうなと。