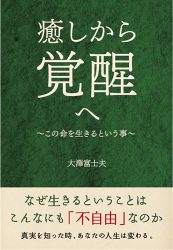学生の頃、フッサールという人の現象学入門という哲学書を読んでいたのですが、それが今の非二元と重なるところがあるかなあと。
そんなことをつらつら思い返していたら、おやっ、社会人になってからもその本を読んでいた記憶があるなと。
あれ、一体どちらの記憶が正しいんだろうか?自分の記憶の曖昧さにはびっくりするしかありません。
そう思って、しばらく記憶を辿っていたら、どちらの記憶も正しかったのではないかと気づくことができたのです。
その本は難解な内容で、読んでも気持ちよく理解することができなかったのですが、それでも気になっていたのですね。
それで、学生の時も、そして社会人になってからも、断続的に読んでいたということに思い当たったのです。
とはいうものの、内容的にはほとんど頭に入っておらず、もうこの歳で難しい書物と格闘するのはごめんだし。
というわけで、いつものAI君に聞いたところ、確かに非二元と通ずるところがあるなということがわかったのです。
AI君に言わせると、現象学は、「ものごとを、先入観なしに、その“現れ方“そのものとして見る哲学」ということらしいです。
ただし決定的な違いもあって、現象学は「意識」を出発点としているところであり、非二元は意識すら起こっている出来事に過ぎないというところですね。
こうしてみていくと、非二元ってこれ以上にシンプルなものはない感じがしてきます。