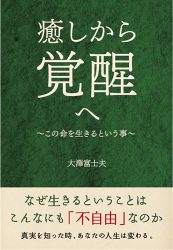私の記憶では、一次方程式を習うのは中学一年生の時だったと思います。例えば次の式 2x=6 があるとして、これを解くと、x=3となりますね。
大人になってこれが解けない人はあまりいないだろうと思いますが、初めて計算式の中に数字に紛れて x というアルファベット文字が入ってくるわけです。
そのせいで、x という文字と3 という数字がイコールだということが、生理的に理解できないという子供がいるらしいのです。
確かに 2+1=3 なら分かるのですが、どうしてxという文字が3という数字と同じなのか?と密かに心の中で不信感を抱いてしまったら、その先の数学の勉強が苦手になっても不思議ではないですね。
こうしたことの心のケアを生徒一人ひとりに対してきめ細かくしていくのは、現実的には難しいことなのかもしれません。
そのくらい人の感性というのは、思っている以上に違いがあるということですね。それが最初のちょっとした違和感を生むのです。
そしてそれが、一つ目のボタンのかけ違いのようにその後にずっと大きな影響を及ぼし続けてしまうわけです。
子供たちに物を教えるということが、どれほど注意深く熱意を持ってなされなければならないかが分かりますね。
私の密かな希望として、子供たちにこのブログでいつもお伝えしているようなことを、できるだけ分かりやすく教えることができたらなと思っています。
ただし、子供たちに興味を持って聞いてもらえるようにできるかどうか、そこが一番大事なところですね。