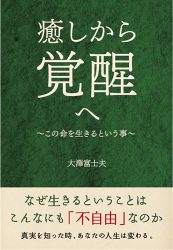小学生の時に、紙飛行機を作って飛ばす遊びが流行ったことがありました。と言っても、学校中でということではなく、同じクラスの男子の中でということでした。
誰の紙飛行機が一番安定して、遠くまで飛んでいくかを競っていたと思います。紙飛行機といっても、折り方は色々あってどの折り方が一番有利かはやってみなければわかりません。
あるとき奇跡的に、真っ直ぐに、しかもほぼ水平に飛んでくれる飛行機を折れたことがあったのです。それはもう、素晴らしいの一言。
自分は有頂天に鼻高々で飛ばしていたのですが、その飛行機がたまたま誰かの足元に着地したと思ったら、その人に踏まれてしまったのです。
一瞬にして飛行機はぺちゃんこになってしまい、恐れていた通り、そのあと元の形に戻して飛ばしてみても、もう以前のような理想的な飛び方はしなくなってしまったのです。
その悔しさといったらありませんでした。故意に踏みつけられたわけでもないので、誰にもその鬱憤をぶつけることもできずに。
そのあと、何度も同じ折り方で紙飛行機を作ったのですが、やはり同じような飛び方をする飛行機を作ることはできませんでした。
その時悟ったのです。この世にあるあらゆるものは、本当にはかないと。いつまでも続いていくものはひとつもないんだなと。
その頃、執着という言葉はきっと知らなかったと思うのですが、何かに心を縛られるのは問題だなあと。すぐに気持ちを切り替えるということを少し覚えたのです。
どんなに大切なものでも、あっという間に消えていってしまうんだなと。それがこの世の掟何だなと妙に納得したのです。
何かに囚われてしまうと、せっかくの人生を存分に楽しめなくなってしまうというのも、どこかで分かっていたように思いますね。